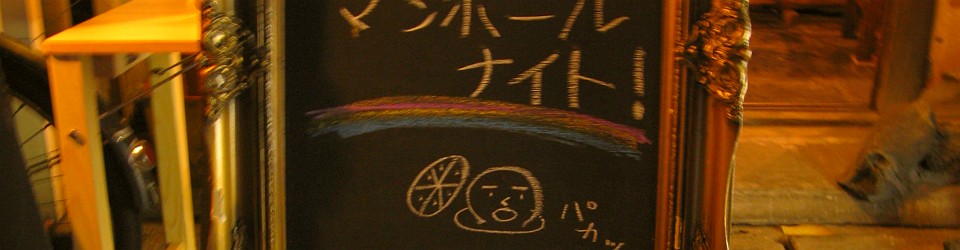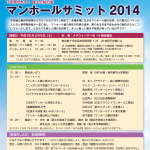野崎駅周辺(大田原市)
大きな地図で見る
駅周辺に、ご当地ゆかりの「那須与一」をデザインした蓋が設置されています。工場見学当日、野崎駅集合時間は13:30ですが、下り列車到着時間は13:04、上り列車到着時間は13:09ですので、それまでの時間、蓋探索をしてみるのもいいかもしれません。
西那須野駅周辺(那須塩原市、旧西那須野町)
大きな地図で見る
野崎駅のお隣にある西那須野駅周辺は、食事のできる店も多く比較的開けていますが、駅周辺にデザイン蓋は設置されていないようです。しかし南赤田地区と東部地区に整備されている農業集落排水処理区域には、可愛らしい「ホタル」と「カジカ」がデザインされた蓋が設置されています。南赤田地区へは北西に2.5㎞程、東部地区へは線路沿いに北北東へ3㎞程と駅からはやや遠い場所になります。もし行かれる場合は、西那須野駅西口からJRバス関東で南赤田地区(西小学校入口バス停)へ行くのが便利です。集落排水の処理区域について詳しくは那須塩原市農業集落排水事業を参照ください。
トコトコ大田原(大田原市)
西那須野駅から東野バスで10分程、市民交流センター(トコトコ大田原3階)の産業展示室では、地元の企業として日之出水道機器㈱栃木工場の展示も行われています。大田原市の紹介記事を見ると、ご当地キャラクター「与一くん」の消火栓・空気弁の蓋も展示されているようです。なお、市営バスも西那須野駅-トコトコ大田原間を運行していますが、非常に遠回りになるのでご注意ください。
道の駅那須与一の郷(大田原市)
マンホールマップに新しい投稿がありました!: 栃木県大田原市本町 http://t.co/zg81BQXU5n – http://t.co/nYOXDLLnox #manhotalk
— #manhotalk_bot (@manhotalk_bot) 2013, 4月 6
大田原市には「那須与一」をデザインしたカラーの蓋も幾つかあるようです。道の駅那須与一の郷には間違いなくカラー蓋が設置されているようですので、早めに出かけて足を伸ばしてみるのもいいかもしれません。東野バス・西那須野駅~五峰の湯線、八幡神社前バス停下車が便利です。
黒羽地区(大田原市、旧黒羽町)
大きな地図で見る
黒羽町は2005年10月に大田原市に編入されていますが、合併前の黒羽町時代の蓋(町の花・木・鳥「ヤマユリ」「スギ」「ウグイス」)がまだ残っているようです。カラーの蓋もあるようです。道の駅那須与一の郷と同じ系統のバス(西那須野駅~五峰の湯線)に乗り、黒羽支所前で下車すると上記のカラー蓋の近くです。始発電車に乗る覚悟があれば工場見学にも間に合います。
那須塩原駅周辺(那須塩原市、旧黒磯市)
マンホールマップに新しい投稿がありました!: 栃木県那須塩原市沓掛1丁目2-3 – http://t.co/kaUKRdYYiD #manhotalk pic.twitter.com/ty7UvccFkl
— #manhotalk_bot (@manhotalk_bot) 2014, 8月 27
新幹線を利用して野崎駅へ向かう場合、那須塩原駅で乗り換える(那須塩原-野崎間の乗車券が別途必要になります)こともあるかと思いますが、駅前には合併前の黒磯市の木「マツ」がデザインされた蓋や、市の花「アジサイ」がデザインされた蓋が設置されています。
矢板駅周辺(矢板市)
マンホールマップに新しい投稿がありました!: 栃木県矢板市木幡1655-2 – http://t.co/CMh7omhpRE #manhotalk pic.twitter.com/xN82cY2nVe
— #manhotalk_bot (@manhotalk_bot) 2014, 8月 27
野崎駅のお隣、矢板駅周辺にデザイン蓋は無いようですが、沢地区と境林地区に整備されている農業集落排水処理区域でデザイン蓋が使われています。沢地区へは北東へ3km程、境林地区へは南へ2.5㎞と駅からはやや遠い場所になります。もし行かれる場合は矢板駅より市営バスで「城の湯温泉センター」まで行くのが便利です。集落排水の処理区域について詳しくは矢板市農業集落排水処理施設条例を参照ください。